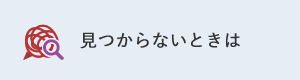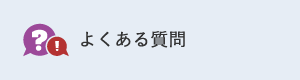越境した竹木の枝の切取り〈民法改正〉
越境した竹木の枝に関するルールが改正されました
これまでは、隣の土地から境界を越えて木や竹の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木や竹の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。
(改正後の民法第233条第3項第1号~3号(抜粋))
(竹木の枝の切除)
1 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
2 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
3 急迫の事情があるとき。
相当の期間内とは
上記1の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
かかった費用の請求について
越境した枝の切り取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に費用を請求することができると考えられます。
(民法第703条、第709条)
(不当利得の返還義務)
第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
隣地への侵入について
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます。
(改正後の民法第209条(抜粋))
(隣地の使用)
第209条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
1 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
2 境界標の調査又は境界に関する測量
3 第233条第3項の規定による枝の切取り
関連資料
(令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋)